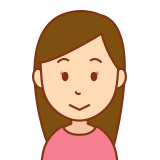
二級建築士の独学って厳しそう~
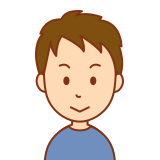
でもスクールに通う時間もないから、独学で挑戦したいんだ。
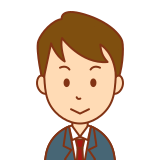
ここでは筆者が独学で二級建築士をパスした勉強法を公開しますので、参考にしてみて下さい!
勉強する際のポイント
私は二級建築士試験に合格し、現在では一級建築士の資格を保有しています。
一級建築士の試験に比べると二級建築士の試験は簡単です。
でもそれは今の状況があるから言えることであって、二級建築士の試験を受けようとしていた当時の私も、なかなか苦労した覚えがあります。
幸い、私は大学の建築学科を卒業し建築系の会社に就職したため、大学・職場の先輩などにはもちろん建築士資格の保有者がいましたので、二級建築士の勉強をするにあたって、様々なアドバイスを受けることができました。
やみくもにやるだけでは、効率の悪い方法を選択してしまい、時間を無駄に消費してしまいがちです。
なので今回は、当時の先輩方のアドバイスを私なりにまとめた「勉強するうえで大切な5つのポイント」を伝授します!
私自身、このポイントを意識して勉強したから合格できたので、皆さんもぜひご参考になさってください。
ポイント①
法令集の線引きしながら覚えようとしない。とにかく法令集の線引きを終わらせる事が重要。
ポイント②
過去問題集やテキストを選ぶ際は、一番得意な科目の解説などを見て、自分に合ったと感じるものを購入する。
(得意な科目でわかりやすい解説=苦手な科目でもわかりやすい解説となっている場合が多いから。)
ポイント③
過去問題集➡️解説➡️テキストの順に1問解くごとに繰り返し読み理解していく。
ポイント④
過去問(5年分〜7年分)を最低3周は繰り返し行う。
ポイント⑤
解いた問題の横に、解説・テキストを読んだ後に、理解度を記入しておく。(1周目〜3周目全て)
上記5つのポイントの中で、私が最も大切だと感じるものは③です。
二級建築士試験に合格したいのであれば、テキスト先行ではなく過去問を先行してやっていきましょう。
とにかく過去問に触れる機会を多くしておく事が重要です。
また、二級の場合はテキスト先行だと勉強範囲が広くなりすぎてしまうため、私は時間ロスが多く非効率な勉強方法だと考えます。
テキストは過去問の後に理解度に応じて活用していきましょう。
私が実践した勉強方法とスケジュール
試験を受ける前年の11月から私の試験勉強はスタート。
まず手始めに、10月に発売されたばかりの「総合資格学院の緑本」(法令集)を購入し、12月中に線引きまで終わらせました。
この法令集を選んだ理由として、本自体のサイズが大きいので1ページ当たりの情報量が多く、ページ数が少ない=めくるページ数が少なくて済むからです。
どういうことかというと、決してページをめくるのすら面倒で横着しているというわけではなく、試験本番(建築法規)では限られた時間内で求められた答えを法令集から探す必要があります。
そのような場合、例えばコンパクトで持ち運びに特化したような物より、このような大判の法令集のほうが答えを探しやすく、時間のロスも少ないです。
後は、一緒に付いてくるハガキを出せば線引きの仕方が掲載された本が届いて、その通りに線を引けば試験対策済みの法令集を作ることができるからです。
実際に身の回りの建築士試験合格者の先輩も使っていたという方が多く、合格者数を多数輩出している資格学校が販売しており、それらの実績の裏付けもあったため、信頼できると感じたから選びました。
テキスト・過去問題集については、法令集の線引きが終わってから購入。
1月から手をつけ始め、過去問題集➡️正当・解説の確認➡️テキストの順で1問解くごとに、理解しながら勉強していきました。
テキスト・過去問題集の選び方についてですが、わかりやすい・勉強しやすいと感じるかどうかは、その人と本との相性があるで一概には言えません。
一度自ら書店に出向き、実物を見てみましょう。
見ても、どれにすればいいかわからない・迷った場合、選択肢の中に総合資格学院のものがあれば、それを購入することをおススメします。
私も使って合格することができました。
試験は5肢択一問題ですが、正解ばかりに注目せず、全ての設問についての解説の確認、テキストで注意点やポイントをチェックすることが重要です。
ここで、ワンポイントアドバイス。
これをやる事で、1周目、2周目、3周目の理解度が見えて、自分の得意な問題と苦手な問題が把握できます。
3周目終わった時点で、〇がついていない過去問題のみチェックを行い、解説・テキストを集中して確認しましょう。
それでも、どうしても苦手で理解できない2〜3問は、切り捨てました。
例えば私は、接着剤関係の問題が苦手だったので、切り捨てて運任せにしました。
もちろん、全ての問題について理解はできていたほうがいいですが、わざわざ苦手なこの1問を理解する為の時間があれば、他の問題についての理解度を深める勉強時間に回したほうが効率的だと判断したからです。
学科試験の勉強を始めたばかりの1周目は、はっきりいってよくわからず、理解がないので当たり前に得点も低かったのですが、諦めずに、とにかく過去問題集を解いたら解説とテキストの確認をするということを一つ一つ丁寧に繰り返していきました。
すると、2回目、3回目と繰り返していくごとに理解が深まっていき、最終的には過去問はほぼ間違えない、という水準まで内容を理解することができました。
当初は過去問を3回も繰り返すことを目標としていましたが、過去問題集を解くたびに問題を解くスピードも速まります。
私は学科試験までの6ヶ月で過去問題集を5周分繰り返しました。
私は過去問題集以外にも、ポケット問題集を持ち歩き、1問でもいいから、解いて解説を確認するという事もやりました。
スポーツも勉強もやればやっただけ実力と自信が付きます。
ちょっとした隙間時間も有効に使いましょう。
実際、ここまでやると試験日が近づいても、特に不安だと感じることはありませんでした。
結果として、試験当日全て問題を解き終わり、見直ししながら自己採点をしてみると、迷った問題が全て間違ったとしても、各科目15点以上(法規は20点以上)かつ総合得点70点以上は、取れている事がわかり、試験中にも関わらず合格を確信することができました。
問題よりも自分の名前と受験番号を書き間違えてないか、不安になって確認したぐらいです笑。
後日試験結果を確認すると、全国でもかなりの上位の成績での合格でした。
この時は完全に調子に乗っていましたね。
・・・一級建築士試験で、痛い目に遭う前兆とは知らずに。笑
(この話は、後で1級建築士試験について記載の際に触れます。)
二級建築士試験の学科については、先に上げた5つのポイントを押さえ、私の勉強方法も参考にしていただき、まじめにコツコツやっていけば、合格できます!
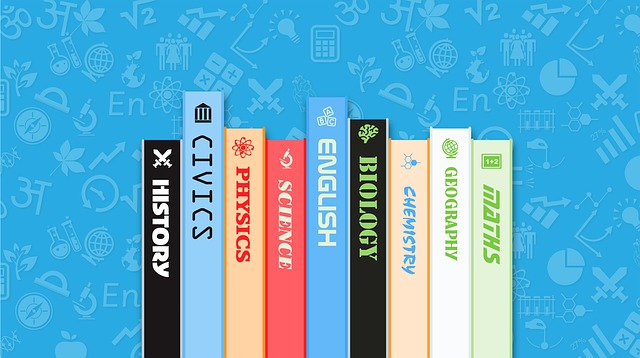


コメント