二級建築士とは
小さいころ、「大工さんになりたい!お家を建てたい!」という夢を持っていた人って、いつの時代になっても一定数いると思います。
いざ実際に建物を建てるとなると、大工さんだけではなく他にも多くの人、各分野の専門知識を持った方が関わります。
その中の一人が建築士資格を持った建築士です。
建築士は、図面が描く技術があるから・建築系の仕事をしているから、というだけではなることはできません。
公益財団法人建築技術教育普及センターが主催する『建築士試験』に合格する必要があります。
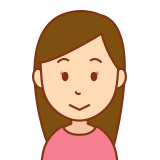
自分で家を設計できるなんて夢があるな~
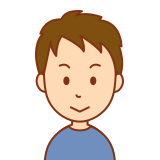
僕は大きなビルや橋なんかも設計してみたいな~
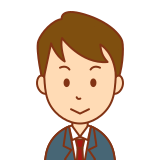
一口に建築士と言っても、「木造建築士」「二級建築士」「一級建築士」と三種類あり、今回は二級建築士についてご紹介します。
「木造建築士」「二級建築士」「一級建築士」、いずれも建物の設計をすることができる、という共通点があり、一級建築士の場合、設計することができる建物の規模に制限がありません。
しかし二級建築士の場合、一級建築士に比べて設計できる建物の規模と構造に制限があり、木造建築物は3階建までです。高さ13m、軒高9mを超える建物、建築物の延べ面積が1000㎡以上の建物の設計はできません。
木造建築物以外でRC造や鉄骨造の場合はさらに制限が厳しくなり、延床面積は100㎡以下に抑える必要があります。
日本において一般的な住宅は木造住宅であることが多いため、ハウスメーカーや不動産屋などで活躍していることが多いのが二級建築士です。
試験制度
二級建築士は、『公益財団法人建築技術教育普及センター』が試験を主催する国家資格のひとつです。
試験は、学科試験が例年7月第1日曜日、設計製図試験が9月第2日曜日に行われ、どちらも合格することで、二級建築士試験に合格したことになります。
学科試験について内容を詳しく見ていきます。
問題は全部で100問。
5つの選択肢の中から1つの正答を選択するマークシート方式で、出題される内容は、学科Ⅰ(計画)・学科Ⅱ(法規)・学科Ⅲ(構造)・学科Ⅳ(施工)となっており、各学科から25問ずつ出題されます。
一気に100問分の試験を受けるのではなく、10時~13時(3時間)に学科Ⅰ・学科Ⅱ、1時間10分の休憩をはさんで14時10分~15時10分(3時間)に学科Ⅲと学科Ⅳを受けます。
各学科で13点以上かつ総得点60点以上が合格点です。
設計製図試験は、ぶっつけ本番で行われるというわけでなく、例年の試験日である9月第2日曜日の約3か月前である6月上旬ごろに、試験を開催する建築技術教育普及センターより課題が公表されます。
ちなみに令和元年の試験では、「夫婦で営む建築設計事務所を併設した住宅(木造2階建て)」
という課題が出されており、試験当日は11時~16時の5時間以内にその課題に沿った
といった8種の図面作成が求められました。
各図面の評定は、
と4段階で評価され、ランクⅠのみ合格とされます。
令和元年の二級建築士設計製図試験の受験者数は10,884人、合格者数は5,037人なので、46.3%ほどの合格率でした。
受験資格 受験基準
2級建築士は誰でも自由に受験することができる資格ではありません。
ある一定の条件を満たす必要があります。
その条件というのが建築士法第15条により定められているので、要点をまとめて以下に記載します。
建築士を志す若年層は建築系の学校に進学するかと思いますが、そういった方はすぐ受験することができます。
学生時代、特に建築関係の学校でなかったとしても、仕事が建築関係で7年以上の実務経験があれば、2級建築士の試験を受験することができます。
建築関係の実務経験というとざっくりしていますが、
この3つが該当します。
受験資格を満たすためには様々なルートがありますが、実際に試験を受けている人はどうでしょうか。
令和元年の学科・製図試験合格者の中からそれぞれの属性を見てみましょう。
令和元年「学科の試験」合格者(全国)8,143人の主な属性
受験資格別
区分…構成比
学歴のみ…74.5%
学歴+実務…8.7%
実務のみ…16.2%
建築設備士のみ…0.6%
令和元年「設計製図の試験」合格者(全国)5,037人の主な属性
受験資格別
区分…構成比
学歴のみ…77.0%
学歴+実務…8.8%
実務のみ…13.8%
建築設備士のみ…0.4%
どちらも7割以上が学歴のみ(建築関係の学校卒業者)ということがわかりますね。
実際に建築士として活躍する多くの方は、建築系学校の卒業者です。
しかし、学校を卒業しなくとも実務経験を積んで資格に合格し、建築会社等で建築士として活躍することは不可能ではありません。
取りたいと思った時に受験することができないため、数年単位の準備を要する資格というのがデメリットかもしれませんが、合格できれば普段の仕事(実務)はもちろん、就活も有利に進められるかもしれませんね。



コメント