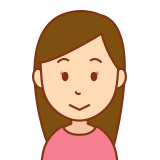
宅建の試験勉強ってどう進めればいいの?
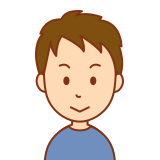
チャレンジするたび、途中で挫折しちゃうんだよ!
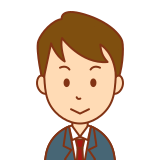
ここでは筆者の試験勉強の体験から、どう進めれば独学一発合格に近づけれるのか?お話しします!
参考書は3回読む
私は宅建の勉強を4月、試験まで半年という時期に開始しました。
実際に行った勉強方法ですが、”まず3回”参考書を読みました。
1回目は宅建試験ってどんな内容なのだろう?といった感じで、あまり理解しようとはせず、全体像を掴むためにパラパラと読みます。
資格の受験勉強で参考書を読む場合に「最初のページから全部覚えよう!」っていう感じで意気込んで勉強を始めるため、途中で息切れして挫折してしまう。
そして、次の年に再挑戦するも同じパターンを繰り返してしまい、結局テキストの最後までたどり着けなかったと言うような結果にならないように気を付けました。
2回目からは理解していくつもりで、参考書に時々ある練習問題を解きながら読み進めました。
この2回目の学習に最も時間を割きました。
1回目の学習とは違い、理解しづらい項目は何度か繰り返したり、1回目で理解できるような項目は軽く流したりと言うような要領です。
3回目は、2回目よりもさらに理解を深めていきます。
3回目の参考書読みから、『苦手だな』、『わかりにくいな』という項目もわかり始めてきました。
参考書を3回読み終えてから、過去問に取り掛かりました。
過去問は10年分5回繰り返す
試験までの間に、トータルで過去問10年分を5回繰り返しました。
まず、過去問を解く際に私が注意していたことは、当てずっぽうで回答しないことです。
たまたま正解してしまうと、わからないものがわからないままになってしまいます。
「これとこれで迷った」「これは絶対に違う」等、過去問解答中にメモで残しておくと、後で確認する際に便利です。
間違った問題は答え合わせ後、すぐに参考書を読んでどう解釈するのが正しいのか、必ず確認していました。
過去問を繰り返していくと、『きちんと理解し正解できる問題』『理解が足りず毎回間違えてしまう問題』の傾向がわかってきます。
そういった問題がわかってきたら、過去問に取り掛かる前に苦手な分野を参考書で確認してから過去問を解く、ということも行っていました。
私自身はあまり記憶力に自信がないし、どうしても理解できない問題については無理に取り組まず切り捨てました。
「勉強すればできそうな項目」「相当な時間を要しても効果が少ないな?と言う項目」を取捨選択しました。
要は、難し問題は”あきらめた”ってことです。
それで結果的に合格することができたので、良い判断だったと思います。
このように勉強を進めていくと段々と点数が上がっていき、4周目あたりにはほとんどの年度で40点以上、5周目には満点に近い点数を取ることができました。
1日で根詰めて集中力のない状態で何十時間も勉強しても、まったく意味はありませんので、少しずつコツコツ頑張っていきましょう。
まとめ
私の実践した勉強方法をお話ししてきました。
まとめると…
いい方法だな?っと感じてもらえたら、うれしく思います。
参考にしてみてください!
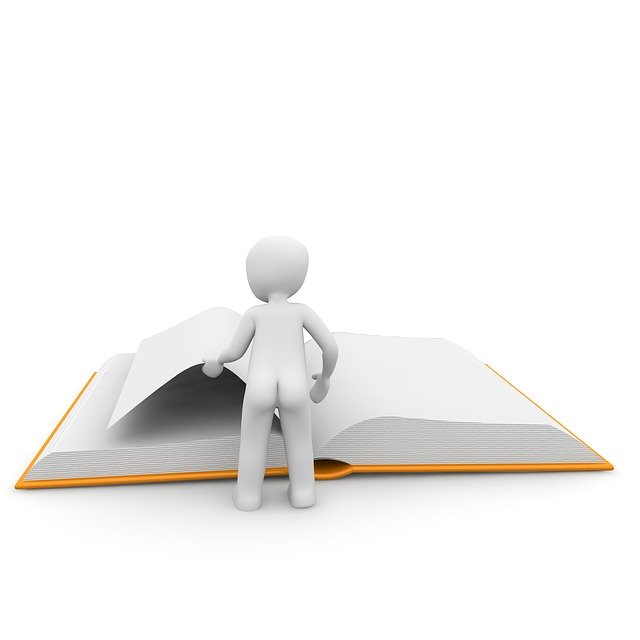


コメント