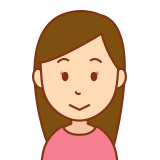
宅建って実生活にも役に立ったりするのかな?
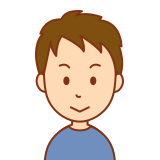
宅建もってなくても、不動産の仕事には就けるでしょ?
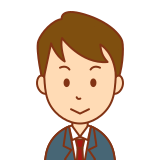
ここでは、宅建と言う資格が仕事上だけでなく実生活でも、どのように関わってくるものなのかを、お話しします!
宅建を取得するということとは?
宅建は、「ただのパフォーマンスの資格か?」
「ルール上持ってなきゃいけないから取得する資格なのか?」
「就職活動に使うのか」、「転職活動に使うのか」、「実務の知識で使うのか」、「給与UPの手段で使うのか」、「独立で使うのか」、「独占業務で使うのか」、「出世で使うのか」…
いろいろな思惑があるとは思いますが、宅地建物取引士という資格は『宅建業者としては必須の資格』です。
その理由は以下の点です。
1.開業のために必要
宅建業法第三十一条の三では、「宅建業者(不動産屋等)は宅建士がいなければならない」ということを謳っています。
就職活動の際の武器として宅建取得を検討されている方は、既に宅建業者として成立している会社(一人は宅建士がいる会社)に入社するため、これから宅建業者として独立・開業したいとお考えの方にとっても重要なポイントです。
2. 5人に1人以上は宅建士
『1.開業のために必要』の続きのようなものですが、宅建業法第三十一条の三をさらに詳しく見ていくと、「宅地建物取引業者は、〇〇事務所等の規模、XXを考慮して、△△宅地建物取引士を置かなければならない。」としています。
この「事務所等の規模」という点がポイントで、一つの事務所の従事者の5人に1人以上は宅建士である必要があります。(法定人数)
宅建業者が採用活動をしていくと、もちろん人が増えていくわけですが、一つの事務所に10人の従事者がいれば2人、従事者が100人いれば20人は宅建士がいる必要があります。
宅建業者は宅建士の法定人数が規定より下回った時、2週間以内に設置要件に適合させるための措置を取らなければならず、違反した場合は国土交通大臣又は都道府県知による指示・業務停止処分、最悪宅建業者としての免許の取消処分となってしまいます。
ですから、宅建業者は法定人数を下回らないためにも宅建士は多い方がいいので、不動産業界で働きたい方は、宅建を取得していると採用される可能性がグンとあがるはずです。
3.宅建士にしかできない独占業務がある
宅建士にしかできない独占業務(法定業務)は、『重要事項の説明をする事』、『重要事項の説明書(35条書面)に記名押印する事』、『契約書(37条書面)に記名押印する事』の3つあります。
これらの業務は必ず宅建士が行わなければなりません。
もし違反した場合、監督処分を受けます。
重要事項説明義務違反があった場合の業務停止日数については、
「書面を交付したけれども、書面に重要事項の一部を記載しなかったり虚偽の記載をした場合、説明をしなかった場合、取引主任者以外の者が説明をした場合」
:関係者の損害の発生の有無や程度によって、7日~30日
「書面を交付しなかった場合」
:関係者の損害の発生の有無や程度によって、15日~60日、としています。
公益社団法人全日本不動産協会「重要事項説明義務違反に対する監督処分」(2020/04/28アクセス)
以上3点から、宅建という資格はパフォーマンスで使うというよりは、実務を行ううえでなくてはならない資格ということがお分かりいただけたかと思います。
実生活で役に立つのか?
宅建は『実生活で役立つか否か?』 『資格を持ってれば、どういう事に生きるか?』 『持ってる事で人生豊かになるか否か?』
宅建を持っていて実生活に役立つかどうかについてですが、特にわかりやすいのは不動産取引をするときですね。
新生活でアパートを借りる・家を建てるために土地を買う・建売住宅を買うといったとき、消費者の自分が宅建を持っていれば、営業マンも多少は意識して、ミスをしないようにいつもより気を付けて対応します。(私も意識しますしね)
あとは多少の実務経験が必要になってきますが、親類・知人等が不動産を売る買う借りる貸すといった取引をするときに相談に乗り、アドバイスをすることができますね。
もちろん宅建業者として、独立開業することもできます。
これらは言わずもがなといった感じですよね。
一般企業に転職活動をする際にも、宅建合格者は法律(民法)の基礎を知っているということで、好印象となるケースも多いようです。
細かい話ですが、いつも何気なくこなしているコンビニ等でなにかを買うという行為だって民法上の売買契約です。
民法というのは普段の生活に密接に関わるため、不動産業以外の方でも宅建を持っていると便利かもしれません。
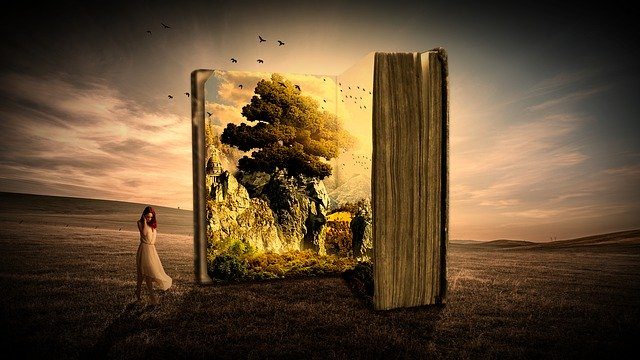


コメント